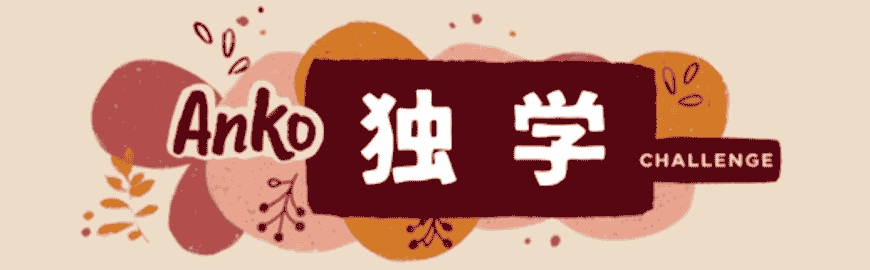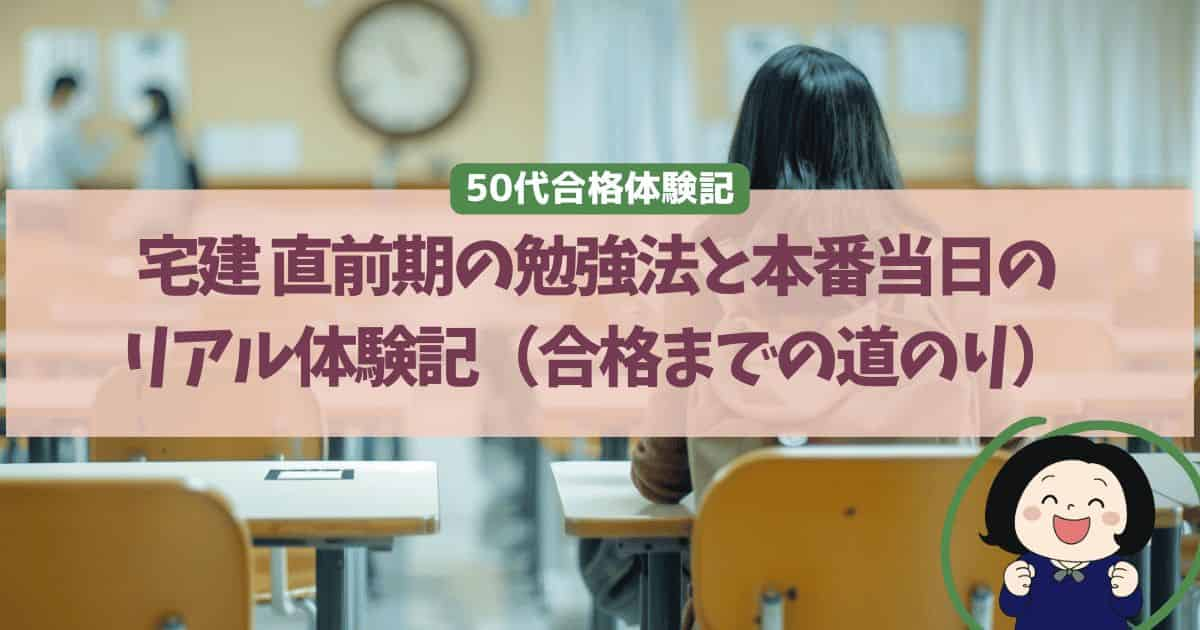宅建試験に向けて「直前期の勉強って何をすればいいの?」と不安になる方も多いと思います。
私自身も模試で点数が伸びず、焦りや不安と戦いながら本番を迎えました。
この記事では、直前期にどんな勉強をしたのか、本番当日の流れや心境、そして合格に至るまでのリアルな体験をまとめています。これから受験する方の参考になればうれしいです。
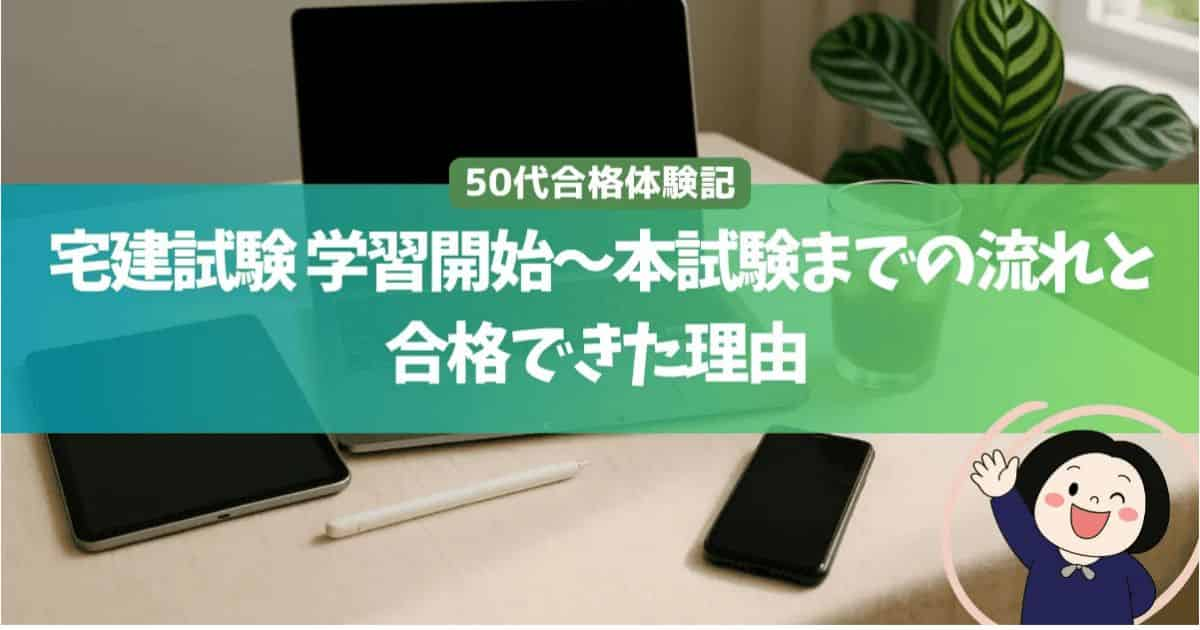
宅建 試験直前期の勉強は「得点源を落とさない」
本番3週間前になって、初めて自宅模試を実施しました。合格ラインは36点前後と言われています。
スタディング合格模試:25/50点

最初のスタディング模試では大敗。そこから“烈火のごとく”勉強を加速しました。
本番1ヶ月前からは生活の中心が勉強。休日は8時間くらい勉強していました。
得点源を落とさない学習
時間に限りがある中で、全体的な復習は試験直前の数日間に回すことに決め、宅建業法と法令上の制限をメインに重点的に学習。得点源を落とさないことを第一にしました。
AI問題復習カスタムモードの活用
スタディングのAI問題復習「カスタムモード」は、苦手分野の克服にとても役立ちました。
特に私は「借地借家法」「35条(重要事項説明)」 と「 37条(契約書面の交付)」に関する問題でつまずくことが多く、カスタムモードで関連する問題だけを抽出して繰り返し解きました。
そして、何より痛感したのは
「宅建試験って似たような言い回しで引っかけてくる」
ということ。最初のスタディング模試で撃沈したのも、誤りの理由まで理解していなかったのが原因でした。
そこで本番に向けては「正解肢だけでなく4択すべてを検証し、どこが正しい・どこが間違いか」を徹底。誤りの理由まで理解する習慣をつけたことで、初見問題にも落ち着いて対応できる力がついたと思います。
「苦手を集中攻略する」ことに特化できるのが、このカスタムモードの大きな魅力です。
- 目的に応じて条件を自由に指定できる復習モード
AI問題復習には「AIモード」と「カスタムモード」の2種類があります。カスタムモードでは、自分で選んだ条件に合う問題だけをまとめて復習できます。 - 苦手問題や過去問にピンポイント対応
「前回間違えた問題」や「要復習にチェックした問題」、「特定の科目やカテゴリー」など、自分の課題に合った問題を重点的に学習できます。 - 出題順の自由設定が可能
「解答日時が新しい順」「問題番号順」「難しいものから(正答率が低い順)」など、復習順も自由に選べます。直前期の対策にもぴったりです。 - 問題数を限定して効率的に
演習可能な問題の中から、出題数を指定して集中演習ができます。スキマ時間や直前期でもムダなく取り組めます。 - 使い方ワンポイント
①「AI問題復習」画面で「カスタムモードを選択」
② 条件を設定(例:「苦手分野+正答率の低い順」)
③ 問題数を指定 → 「問題復習を開始する」でスタート!
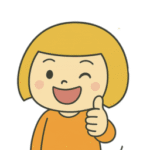 kinako
kinako苦手を集中的に攻略できるので安心ですね
模試は“リハーサル”。点数は・・・散々な結果。
それでも!本試験直前にやった自宅模試の結果は 33点 → 39点 → 26点…。
正直、撃沈続きでした。
第1回:33/50点(本番7日前)
第2回:39/50点(本番4日前)
第3回:26/50点(本番2日前)
『出る順宅建士 当たる!直前予想模試』
東京リーガルマインドLEC総合研究所 宅建士試験部

それでも、本番では 41点で合格ライン突破。模試の点数に一喜一憂する必要はまったくありませんでした。
今振り返れば、あの点数は「合格できない証拠」ではなく、むしろ「合格に近づく材料」だったんです。
大事なのは どこでつまずいたかを知ること。
模試は弱点を洗い出して修正するためのリハーサルにすぎません。
点数自体はただのオマケ。
模試で撃沈しても、本番では大逆転できる──私が41点で合格できたのが、その証拠です。
模試は本番の練習試合。勝ち負け(点数)じゃなく、課題発見の場。
最後に合格点を取れればそれで十分!
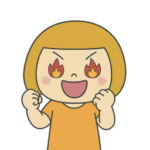 kinako
kinako模試は点数に振り回されず、弱点を見つける材料として活用!ですね
宅建 試験前にやっておいた準備
スタディング 宅建士 直前対策講座
直前対策講座と講師の竹原先生からの激励メッセージが、私に大きな勇気と自信を与えてくれました。特に「ここは今やらなくていい」「ここは必ず確認すべき」というポイントが明確になり、最後の学習の取捨選択がはっきりしました。まさに合格のためのメソッドだと感じます。
本番の前日と当日午前中に受講したことで、忘却する前に試験を迎えられたのは大きなメリットでした。
実際に「この講座を聞いていたから解けた!」という問題もあり、受講の効果を実感しました。
もし余裕があれば「試験の1週間前に一度、直前にもう一度」という受講スタイルが理想だと思います。そうすれば知識も定着し、さらに気持ちの余裕を持って本番に臨めたでしょう。
そして何より、竹原先生からの励ましの言葉は、不安でいっぱいだった私にとって心強い支えでした。試験会場に向かう途中もその言葉を思い出し、背中を押していただいた気持ちでした。
学習時間:3時間30分のコンパクト整理講座
全科目(権利関係・法令上の制限・宅建業法・税その他)の出題予想論点を短時間でいっきに学べます。
直前期のラストスパートに最適
忙しい直前期でも、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間に効率よく学習できます。
苦手科目の最終確認にぴったり
権利関係・宅建業法・税その他といった各分野の予想論点が厳選されており、何を最優先で学ぶべきか迷わなくてOK!
視聴と復習もスマホ・PC・タブレットで自由自在
媒体を問わず使えるので、自分の生活スタイルに合わせた受講が可能です。
 anko
anko講義のスライドをPDFでダウンロードしてスマホで確認できるようにしました。
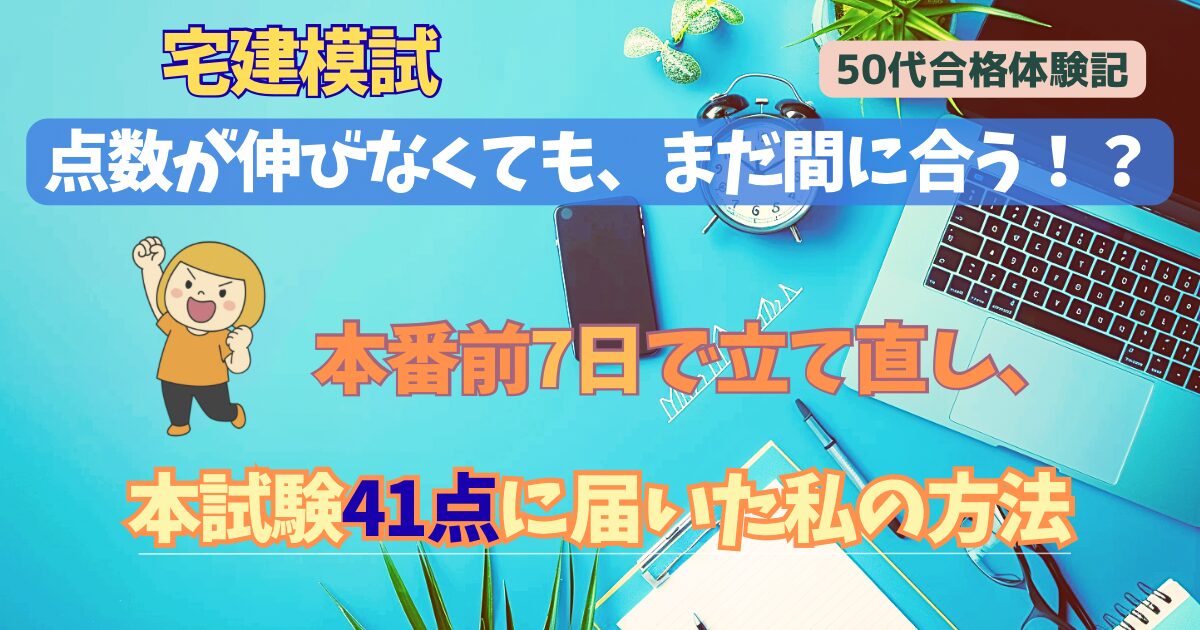
試験当日に必要な持ち物リスト【3日前までに準備】
私は心配性なので、持ち物リストはかなり念入りにチェックしました。
当日の朝に慌てて用意すると、忘れ物や余計な不安につながります。
持ち物は試験日の3日前までには揃えておくと安心です!!
早めに準備しておけば、試験直前は勉強や体調管理に集中できますし、「もう大丈夫」と気持ちも落ち着きます。
そして毎日確認していました(笑)
持ち物のチェックは万全にしておきましょう!
- 受験票(もしもの紛失などの対策に、写真を撮っておく)
- 腕時計(スマートウォッチや置時計の利用不可)
- BかHBの鉛筆又シャーペン・消しゴム(替芯とシャーペン2〜3本・消しゴム2〜3個用意)
- あると安心アイテム
- 直前復習用のアイテム(ノート・テキスト・ipadなど)
- 本人確認書類(保険証・免許証・マイナカード)は受験票紛失などのトラブル対策に
- 薄手のカーディガン(会場の冷暖房対策用)
- 直前復習用のアイテム(ノート・テキスト・ipadなど)
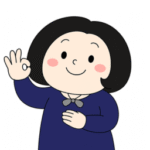 anko
anko試験会場への行き方や所要時間をチェックしておくと安心です!
試験直前の過ごし方と体調管理
私は心配性でお腹も弱いので、試験前の体調管理には特に気をつかいました。
前日は 消化の良い食事・アルコールを控える・辛い食べ物は摂らない・適度な運動(ウォーキング) を意識。試験前にラーメンなんて絶対に無理なタイプです。
また、風邪をひかないようにすることや、感染症の予防にも注意。睡眠はしっかり確保し、疲れを溜め込まないように気を配りました。年齢的にも、無理をすると数日引きずってしまうので「無理をしない・休むことも大事」と心に言い聞かせていました。
ここまで体調管理に気を配りながら過ごしてきましたが、やはり一番の山場は「試験当日」です。前日は消化の良い食事やウォーキングで整え、睡眠も十分にとったつもりでしたが、心配性の私はやはり不安が尽きませんでした。特に最大の懸念は「トイレ問題」。宅建試験は途中退席ができないため、「大丈夫かな…」という不安は最後まで拭えませんでしたが、本番になれば大丈夫!と自分に言い聞かせ、不安を少しずつ和らげていきました。
そんな緊張を抱えながら迎えた、いよいよ本番当日の朝──。
宅建 試験当日 流れと心構え
試験当日の朝は、5時半からスタディング竹原先生の直前講座を受講し、知識を最終確認しました。この“ひと押し”が記憶を呼び起こし、自信を持って会場に向かう原動力となりました。
会場(大学)には12時ごろ到着しましたが、すでに長蛇の列。建物への入場だけでも20分かかり、想定していた復習時間が削られてしまいました。改めて「もっと早く到着しておけばよかった」と痛感しました。これから受験する方には、余裕をもった到着を強くおすすめします。
教室に入ると、席はほとんど埋まっていました。幸い時計は設置されていましたが、会場によってはない場合もあるそうです。持参しておくと安心できます。
最後の仕上げは「慌てないこと」。直前の復習と準備のおかげで、気持ちを落ち着けて本番に臨むことができました。
宅建 試験 心構え
① 余裕をもって到着することが大事!
会場に着くと受験生の多さにびっくり。入場するだけで20分もかかってしまいました。早めの到着をおすすめします
②自分の世界に集中する
隣にどんな人が座るかは運しだい。ちなみに私の隣は落ち着きなくずっと動いている男性でした…。雑音の中でも集中できるよう、普段から慣れておくと安心です。
③時間配分を意識する
宅建業法や法令上の制限から解き始めるのがセオリーですが、私は1問目の権利関係から順番に解きました。理由はマークミスが怖かったから。
わからない問題は飛ばすけど、マークずれにだけは要注意。
難問は直感で答えて、確実に取れる問題に力を注ぎました。
④ 問題文は落ち着いて読む
試験開始直後は緊張で頭に入ってこないこともあります。でも焦らず、エンジンがかかるまで待ちましょう。

⑤ 不安になったら深呼吸
「やばい、わからない…」と思ったら一度深呼吸。リセットすると、また集中できます。
⑥ 見直しはケアレスミス重視
マークミスや自分のクセを意識して見直すのがおすすめ。焦って読み違えたらもったいないです。
⑦ 最後まで諦めない、でも執着しすぎない
知らない問題が出たら「みんなも同じ」と割り切ること。
ちなみに私は令和6年の問42でフリーズしました。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に関する問題…。見直しても結局わからず、不正解でした(笑)。こういうこともあります。
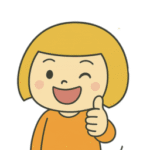 kinako
kinakoシンプルに言えば、落ち着いて前に進むこと
宅建 試験 あっという間の2時間
全て解き終わった時点で残り20分。
- あやふやな回答だった2問を見直し
- マークミス・記名漏れをしつこく確認
- マークした番号を、マークシートから問題用紙にメモ(合格発表までの間、マークミスをしているかも、という不安に陥らないため)。
そして 試験終了。
「あっ」という間の2時間でした。ほんとうに一瞬で終わった…。
すべての問題を解き終えたものの、手応えはほとんどゼロ。
「良くて32点くらいかな…」と半ば諦めの気持ちを抱えながら、「終わった…」という安堵と、どっと押し寄せる疲れとともに、会場をあとにしました。
宅建試験を受けて、振り返って思うこと
自己採点でまさかの展開!
「また来年もか…」と思いながら、居酒屋でささやかに“お疲れ様会”。
ひと通り腹ごしらえをしてから、解答速報を開き、ドキドキしながら自己採点を始めました。
ところが──答え合わせを進めると、意外にも正解がポロポロ出てくる!
「え?これも合ってるの?」「まさか!」とワーワー騒ぎながら、嬉し涙を流しつつマークを確認。何度も何度も繰り返しました。
そして最終的に出た点数は、なんと 41点!
あの瞬間の驚きと安堵と喜びは、今思い出しても笑えてしまいます。

ちなみに、採点場所を「個室居酒屋」にしておいたのは大正解。
「惨敗して号泣しても大丈夫なように」と思って選んだのですが、まさか嬉し涙で正解になるとは(笑)。
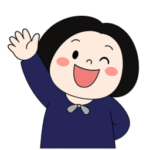 anko
anko直前の模試でズタボロだったけど、本番で奇跡は起きました!
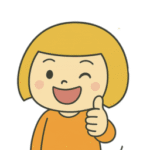 kinako
kinakoとにかく受験会場に足を運んで! そこで未来が変わります!
模試の点数に振り回されない
- 模試はあえて難しめに作られている
- 模試の点数に一喜一憂しすぎず、直前期は「得点源を落とさない勉強」に徹する
- 体調管理と当日の準備が最重要
あのとき、受験をやめずに挑戦して本当に良かったと思います。
過去の自分に声をかけるなら──
「よくやった!最後まで頑張ったから今が楽しいよ!」
 anko
ankoこんな私でも、気づかないうちに力がついていました。今のあなたの努力も、きっと同じように実を結びます。どうかその努力を信じてください!